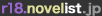今よりも一歩前へ ~掌編集・今月のイラスト~
「行くぞ!」
「うん! 行こう!」
小夜子と和彦は千人ほども集まった聴衆が待ち受けるステージに飛び出して行った。
小夜子は日本生まれの日本育ち、熱心に勉強して英語はそこそこ喋れるようになったがネイティブには程遠い、思考も日本語だ。
だが、その容姿はと言えば到底日本人には見えない。
褐色の肌、銀色の髪、そして左が茶色で右が青の瞳。
もちろん何代にもわたる生粋の日本人ならそう言った容姿にはならない、小夜子の父はエジプトの血が入ったクォーター、母はギリシアの血が入ったクォーターなのだ。
父と母も外国の血を感じさせる容姿ではある、しかし、それは日本人としての範疇を逸脱してはいない、『ちょっと外人っぽいかな?』と言う程度のものだ。
父の肌は少し浅黒いものの、髪と瞳は黒、肌の色だって日焼けサロンに通い詰めていたりサーフィンなどで年中海に入っている日本人よりも白いくらいだ。
母はと言えば、日本人としては色白な方、髪の色はやや茶色がかっていて、瞳も茶色っぽく見える、だが、今時の茶髪はもっと茶色いし、瞳の色だってカラーコンタクトを入れているようなレベルではない。
ところがその二人の間に生まれた小夜子は曾祖父と曾祖母の遺伝子を色濃く、そして半々に受け継いでいた、生まれて来た赤ん坊を見て、両親はいかにも日本的な小夜子と言う名前を付けた程に。
幼い子供と言うのは、ある意味残酷だ。
自分の言葉が持つ意味を考えずに思ったことをずけずけと口にしてしまう。
「サヨちゃんって真っ黒~」
「どうして髪の毛が白いの?」
「目の色が片っぽづつ違う~、変なの~」
そう言って、無意識に距離を置こうとする。
ごく小さい頃、小夜子はどうして避けられるのかわからなかったが、幼稚園に入る頃にはだんだんと自覚するようになってしまう、自分はここでは異質なのだと……。
そのことは小夜子の性格にも影を落として行く。
「遊ぼ~」と近付いても、何となく引かれる、仲間外れにされないまでも、どことなく打ち解けられない、それでは積極的になれと言う方が無理な話だ。
勢い、小夜子は一人遊びにふけるようになって行く、とは言え、人形遊びにしてもおままごとにしても一人では面白みは半減だ、小夜子は次第に絵本の中に自分の世界を見つけるようになって行った。
絵本の中には、自分が今いる世界とは違う世界が広がっている、そこには白い肌や褐色の肌の人々がいて、金髪や赤い髪をした人々がいて、青い瞳や茶色の瞳の人々がいる、それが異質な存在としてではなく生き生きとしている……絵本が児童文学にとって代わるようになっても同じこと、小夜子は読書に居場所を見つけ、生き方を学んで行った。
実のところ、小学校も高学年ともなると、小夜子を見る周囲の目は変わって来ていた。
小夜子の容姿を、むしろ格好良いと思う同級生たちも多くなり、密かに恋心を抱く男子も少なくなかったのだ、だが、小夜子が自ら自分の周りに張り巡らせてしまったバリアは、小夜子自身が外に向ける目も遮断してしてしまっていて、それに気づくことはなかった。
中学に上がると、小さな転機がやって来た。
小夜子の容姿に目を付けた演劇部が熱心に誘いをかけて来たのだ。
自分の『異質さ』は特徴にもなる……初めてそれに気づかされた小夜子は、演劇部に飛び込んだ、そしてその年の学校祭、小夜子は一年生ながら主役に抜擢され、喝采を浴びることになった……。
世界がガラリと変わった……ごく当たり前の公立中学校の、特に受賞歴もないごく当たり前の演劇部、生徒と父兄以外には見向きもされない学校祭での演劇……しかし小夜子にとっては人生を変えるような大きな出来事だった。
それ以来、積極的にクラスメートに溶け込もうとし、明るく振舞うようになった小夜子、そんな小夜子をクラスメートたちは好意的に受け入れてくれた。
しかし、演劇も万能ではなかった、小夜子はその容姿故に演じられる役柄が限られる。
小夜子に合わせて演目を選んでばかりいるわけには行かない……小夜子の輝きは流れ星のように消えたかと思われた。
だが高校に進学すると、もう一つの転機が訪れた。
二学年上、三年生の男子、和男からバンドに誘われたのだ。
バンドと言っても正確にはデュオ、子供のころからピアノに親しみ、キーボードを自在に操って作曲もこなす彼は一年生の時から学園祭のスターだった。
そして三年生になった今、自分が求める音楽に追随してくれるメンバーを見つけられずにいた彼だったが、母譲りの美声が演劇の発声練習で磨かれ、父譲りのリズム感を血の中に持つ小夜子に注目し、誘いをかけて来たのだ。
演劇に限界を感じていただけに、小夜子はその誘いに応じ、それまではあまり興味を持っていなかった音楽に真剣に取り組むようになった。
元々が内向的な性格だった小夜子は、ひとたび没頭すると大きな集中力を発揮する、そして傍らにはいつも、音楽に詳しく才能豊かな和男がいる。
こうして、和男のキーボードと小夜子のヴォーカルからなるデュオは、学園祭で喝采を浴びたのだ。
音楽活動は和男の卒業で終わりを告げることはなかった。
大学に進学した和男は、そのキーボードの腕前、ミュージックライターとしての才能を高く評価されたが、数ある学生バンドからの誘いには乗らず、まだ高校生だった小夜子を相棒としてデュオでの活動を続け、その活動の場をライブハウスに求めて行ったのだ。
そして三年後、その音楽性が評価されてCDデビューを果たすこともできた。
しかし、専門家たちの高い評価と人気は一致しない。
CDの売り上げはあまり伸びず、二人は相変わらずライブハウスで演奏する日々……。
それに業を煮やした事務所は積極的に売り込みをかけ、とある夏のロックフェスに二人の出演枠を確保することに成功した。
延べでは十万人を軽く超える聴衆を動員するフェスだが、二人の出番は会場間もない午前中の時間帯、その時間帯に会場に来ているのはよほどの暇人か、飛び切りの新星が現れないかと期待している熱心なロックファンだけ、サブ会場とは言え一万人を収容できる野外ステージも聴衆の入りは一割程度に過ぎないことは過去の実績が物語っている。
それでも、普段は百人にも満たないライブハウスで活動している二人にとっては大きなチャンスだ。
「おい、小夜子、何をし……え? その衣装は……」
練習場所にしているスタジオでTシャツを脱ぎ捨てた小夜子。
真面目一方で、四年も活動を共にしている小夜子に手を出そうともしない和男は、その行動にうろたえたが、Tシャツの下から現れた衣装を目にして更に絶句した。
「やり過ぎ……かなぁ……」
自信なげに小さくなった小夜子だったが、和男はその大胆な衣装に身を包んだ……いや、実際には肝心なところだけを申し訳程度に覆っただけの小夜子から目が離せない。
「あのね……今度のフェスって、あたしたちにとっては初めての大きなチャンス、そこで受けなければ最後のチャンスになるかもしれないでしょ……だから……」
「うん! 行こう!」
小夜子と和彦は千人ほども集まった聴衆が待ち受けるステージに飛び出して行った。
小夜子は日本生まれの日本育ち、熱心に勉強して英語はそこそこ喋れるようになったがネイティブには程遠い、思考も日本語だ。
だが、その容姿はと言えば到底日本人には見えない。
褐色の肌、銀色の髪、そして左が茶色で右が青の瞳。
もちろん何代にもわたる生粋の日本人ならそう言った容姿にはならない、小夜子の父はエジプトの血が入ったクォーター、母はギリシアの血が入ったクォーターなのだ。
父と母も外国の血を感じさせる容姿ではある、しかし、それは日本人としての範疇を逸脱してはいない、『ちょっと外人っぽいかな?』と言う程度のものだ。
父の肌は少し浅黒いものの、髪と瞳は黒、肌の色だって日焼けサロンに通い詰めていたりサーフィンなどで年中海に入っている日本人よりも白いくらいだ。
母はと言えば、日本人としては色白な方、髪の色はやや茶色がかっていて、瞳も茶色っぽく見える、だが、今時の茶髪はもっと茶色いし、瞳の色だってカラーコンタクトを入れているようなレベルではない。
ところがその二人の間に生まれた小夜子は曾祖父と曾祖母の遺伝子を色濃く、そして半々に受け継いでいた、生まれて来た赤ん坊を見て、両親はいかにも日本的な小夜子と言う名前を付けた程に。
幼い子供と言うのは、ある意味残酷だ。
自分の言葉が持つ意味を考えずに思ったことをずけずけと口にしてしまう。
「サヨちゃんって真っ黒~」
「どうして髪の毛が白いの?」
「目の色が片っぽづつ違う~、変なの~」
そう言って、無意識に距離を置こうとする。
ごく小さい頃、小夜子はどうして避けられるのかわからなかったが、幼稚園に入る頃にはだんだんと自覚するようになってしまう、自分はここでは異質なのだと……。
そのことは小夜子の性格にも影を落として行く。
「遊ぼ~」と近付いても、何となく引かれる、仲間外れにされないまでも、どことなく打ち解けられない、それでは積極的になれと言う方が無理な話だ。
勢い、小夜子は一人遊びにふけるようになって行く、とは言え、人形遊びにしてもおままごとにしても一人では面白みは半減だ、小夜子は次第に絵本の中に自分の世界を見つけるようになって行った。
絵本の中には、自分が今いる世界とは違う世界が広がっている、そこには白い肌や褐色の肌の人々がいて、金髪や赤い髪をした人々がいて、青い瞳や茶色の瞳の人々がいる、それが異質な存在としてではなく生き生きとしている……絵本が児童文学にとって代わるようになっても同じこと、小夜子は読書に居場所を見つけ、生き方を学んで行った。
実のところ、小学校も高学年ともなると、小夜子を見る周囲の目は変わって来ていた。
小夜子の容姿を、むしろ格好良いと思う同級生たちも多くなり、密かに恋心を抱く男子も少なくなかったのだ、だが、小夜子が自ら自分の周りに張り巡らせてしまったバリアは、小夜子自身が外に向ける目も遮断してしてしまっていて、それに気づくことはなかった。
中学に上がると、小さな転機がやって来た。
小夜子の容姿に目を付けた演劇部が熱心に誘いをかけて来たのだ。
自分の『異質さ』は特徴にもなる……初めてそれに気づかされた小夜子は、演劇部に飛び込んだ、そしてその年の学校祭、小夜子は一年生ながら主役に抜擢され、喝采を浴びることになった……。
世界がガラリと変わった……ごく当たり前の公立中学校の、特に受賞歴もないごく当たり前の演劇部、生徒と父兄以外には見向きもされない学校祭での演劇……しかし小夜子にとっては人生を変えるような大きな出来事だった。
それ以来、積極的にクラスメートに溶け込もうとし、明るく振舞うようになった小夜子、そんな小夜子をクラスメートたちは好意的に受け入れてくれた。
しかし、演劇も万能ではなかった、小夜子はその容姿故に演じられる役柄が限られる。
小夜子に合わせて演目を選んでばかりいるわけには行かない……小夜子の輝きは流れ星のように消えたかと思われた。
だが高校に進学すると、もう一つの転機が訪れた。
二学年上、三年生の男子、和男からバンドに誘われたのだ。
バンドと言っても正確にはデュオ、子供のころからピアノに親しみ、キーボードを自在に操って作曲もこなす彼は一年生の時から学園祭のスターだった。
そして三年生になった今、自分が求める音楽に追随してくれるメンバーを見つけられずにいた彼だったが、母譲りの美声が演劇の発声練習で磨かれ、父譲りのリズム感を血の中に持つ小夜子に注目し、誘いをかけて来たのだ。
演劇に限界を感じていただけに、小夜子はその誘いに応じ、それまではあまり興味を持っていなかった音楽に真剣に取り組むようになった。
元々が内向的な性格だった小夜子は、ひとたび没頭すると大きな集中力を発揮する、そして傍らにはいつも、音楽に詳しく才能豊かな和男がいる。
こうして、和男のキーボードと小夜子のヴォーカルからなるデュオは、学園祭で喝采を浴びたのだ。
音楽活動は和男の卒業で終わりを告げることはなかった。
大学に進学した和男は、そのキーボードの腕前、ミュージックライターとしての才能を高く評価されたが、数ある学生バンドからの誘いには乗らず、まだ高校生だった小夜子を相棒としてデュオでの活動を続け、その活動の場をライブハウスに求めて行ったのだ。
そして三年後、その音楽性が評価されてCDデビューを果たすこともできた。
しかし、専門家たちの高い評価と人気は一致しない。
CDの売り上げはあまり伸びず、二人は相変わらずライブハウスで演奏する日々……。
それに業を煮やした事務所は積極的に売り込みをかけ、とある夏のロックフェスに二人の出演枠を確保することに成功した。
延べでは十万人を軽く超える聴衆を動員するフェスだが、二人の出番は会場間もない午前中の時間帯、その時間帯に会場に来ているのはよほどの暇人か、飛び切りの新星が現れないかと期待している熱心なロックファンだけ、サブ会場とは言え一万人を収容できる野外ステージも聴衆の入りは一割程度に過ぎないことは過去の実績が物語っている。
それでも、普段は百人にも満たないライブハウスで活動している二人にとっては大きなチャンスだ。
「おい、小夜子、何をし……え? その衣装は……」
練習場所にしているスタジオでTシャツを脱ぎ捨てた小夜子。
真面目一方で、四年も活動を共にしている小夜子に手を出そうともしない和男は、その行動にうろたえたが、Tシャツの下から現れた衣装を目にして更に絶句した。
「やり過ぎ……かなぁ……」
自信なげに小さくなった小夜子だったが、和男はその大胆な衣装に身を包んだ……いや、実際には肝心なところだけを申し訳程度に覆っただけの小夜子から目が離せない。
「あのね……今度のフェスって、あたしたちにとっては初めての大きなチャンス、そこで受けなければ最後のチャンスになるかもしれないでしょ……だから……」
作品名:今よりも一歩前へ ~掌編集・今月のイラスト~ 作家名:ST